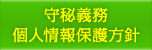遺言

遺言とは、自身の死亡後の法律関係や、財産の配分について定める、最後の生前意思表示です。自身の家族に対し、相続分によらない財産を送りたい、相続人外であるお世話になった人や団体に対し財産を遺したいというような場合に、遺言によって達成することが可能となります。
その一方で、遺言の様々な決まりごとは民法第960条~第1027条において規定されており、作成においても厳格な条件が付されています。様式や作成方式など、様々な条件の中で一部でも条件を逸した場合には、遺言自体が無効となってしまう場合があります。このページでは、遺言の種類や方式・もたらす効果などについて解説をしたいと思います。
目次(項目をクリックすると、該当箇所までジャンプが可能です)
1.遺言の法的性質
遺言には様々な様式がありますが、まずは、遺言そのものがどのようなもので、どのような効果をもたらすのかについて説明したいと思います。
1-1.遺言は要式行為である
遺言は、民法に定める方式に従わなければ、法律上の効果を発揮しません。方式に従っていない遺言は無効となりますので、形式上の条件を厳格に守る必要があります。
1-2.遺言は単独行為である
遺言は、相手方のいない単独の行為です。あまり良くない言い方をすれば、自らの財産を、自らの意思のみで勝手に他人にあげる行為です。本来、契約行為などは行為者と相手方の双方の合意によって成り立ちますが、遺言については相手方(相続人や受遺者)の意思表示は必要ありません。
なお、似て非なる行為として、死因贈与と呼ばれるものがありますが、こちらは贈与者と受贈者との間で交わされる契約行為で、相手方の意思表示が必要となります。
また、共同遺言(2人以上の者が同一の証書で遺言をすること)は禁止されています。例えば、夫婦がともに同じ遺言の中で遺志を記すことはできず、それぞれが別に遺言を作成する必要があります。
1-3.遺言は死因行為である
遺言は、行為者(遺言者)が死亡して初めて法律上の効果を発生させます。
1-4.遺言は、代理に親しまない行為である
遺言は、必ず本人が行う必要があります。遺言能力(遺言を作成する力)は、満15歳以上から認められていますので、親権者等の法定代理人がいる場合でも、遺言の作成が可能です。また、成年被後見人・被保佐人・被補助人等であったとしても、その保護者(後見人等)の同意を必要としません。よって、保護者らによる代理も許されません。
1-5.遺言は、法定されている事項に限りすることが可能である
遺言の中で権利関係を指定・決定できる事項は、法律によって決まっています。決まっている事項以外は指定・決定することはできません。
<遺言によってのみすることができる事項>
①未成年後見人、未成年後見監督人の指定(民法第839条、第848条)
②相続分の指定及び委託(民法第902条)
③遺産分割方法の指定・委託・禁止(民法第908条)
④遺産分割における共同相続人間の担保責任の指定(民法第914条)
⑤遺言執行者の指定及び委託(民法第1006条第1項)
⑥遺留分侵害額請求権に基づく侵害額の負担順位の指定(民法第1047条第1項第二号但書)
<生前でも可能な事項>
⑦認知(民法第781条)
⑧推定相続人の廃除及び取消し(民法第892条~第894条)
⑨祖先の祭祀主宰者の指定(民法第897条第1項但書)
⑩財産の処分(民法第549条、第964条など)
⑪特別受益の相続分への持戻し免除の意思表示(民法第903条第3項)
⑫保険金受取人の変更(保険法第44条)
なお、上記を遺言の共通の性質とした上で、遺言は、その方式により、大きく一般方式と特別方式に分かれます。下記以降では、それぞれの方式に分類される遺言ごとの細かいルールなどについて説明していきます。
2.一般方式による遺言の種類と注意点等
前述の通り、遺言は要式行為のため、法律に定められた方式で作成しないと有効ではなくなってしまいます。様々な方式が存在しますが、それぞれの方式において守るべき事項がありますので、正しい知識を身に着け、不備が無いように作成をしなければなりません。
一般方式による遺言には、「自筆証書遺言」、「秘密証書遺言」、「公正証書遺言」の3種類があります。
2-1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、その名の通り、全文を遺言者の自筆で書き上げる遺言書です。字が書ける人であればどこでも作成することができ、費用もかからない最も手軽な方法です。しかし、その反面作成様式は厳格に定められており、その様式のどれかひとつでも欠けた場合には無効となってしまいます。
2-1-1.自筆証書遺言の要件
①全文自筆でなければならない
必ず全文を自筆で書く必要があります。自筆である理由は、筆跡によって遺言者本人の遺志かどうかを判断することが可能であるからです。よって、既に述べていますが、代理による作成は全て無効となってしまいます。なお、遺言の作成に使う紙の大きさや種類の指定はありません。ペンについても指定はありませんが、例えば鉛筆やシャープペンシルなど、消えてしまうものは避けるのが無難です。
2019年1月13日施行の法改正により、自筆証書遺言のうち相続財産などを記す財産目録については、パソコン・ワープロ等による作成、代筆、不動産の登記事項証明書、通帳の写しなどを添付することが認められました。ただし、取り扱いについては、以下の点についての注意が必要です。
1.財産目録の全てのページに遺言者の署名・押印が必要
2.加除訂正をする場合は、「旧財産目録を新財産目録にする」旨の文書を手書きした上で、新しい財産目録の全てのページに署名・押印が必要
②日付を自筆で書かなければならない
作成日が分かるよう、自筆による日付記入が要求されます。この理由としては、
・遺言の作成日において、遺言の作成能力があったかどうかを判断する材料になる
・遺言は複数回作成することが可能だが、一番新しい日付の遺言が有効となるため、自筆による遺言者本人の遺志を確認する
といった点があります。
日付は必ず「○○年○月○日」と正確に記入しましょう。日付が無い場合は遺言自体が無効となってしまいます。
③氏名を自筆で書かなければならない
こちらについても、前段と同様、遺言作成者を明確にし、本人の遺志であることを証明することが理由です。なお、氏名については、戸籍上の本名でなくとも、例えばペンネームなど、本人を特定できる名称であれば問題はありません。逆に、氏名の記載が一切ない遺言は、筆跡から遺言者が特定できる場合であっても無効となります。
④押印の必要がある
氏名の自筆が要求される理由とほぼ同じです。なお、押印は実印であることを要しません。
⑤日付・氏名の自筆及び押印は、1つの遺言に1箇所で良い
遺言自体が数枚もしくは数ページに渡る場合でも、それらが1通の遺言書として作成されたものであることが確認されれば、そのうちの1部に日付・氏名の自筆及び押印がされていれば遺言は有効となります。ただし、この点は、財産目録を自筆以外の方法で作成するときの注意点と混同しないようにご注意ください。
⑥自筆証書遺言の加除及びその他の変更
加除その他の変更についても厳格な要件が定められています。詳しくは、訂正・加筆・削除したい箇所に訂正印を押し、欄外には、訂正の内容・加えた文字(〇文字加筆等)・削除した文字(〇文字削除)等を記載して行う必要があります。修正テープや黒塗りの訂正はNGです。
この方式に拠らない訂正は無効になりますが、元の遺言までが無効になる訳ではなく、訂正等が無かったものとして扱われます。
2-1-2.保管方法
自筆証書遺言及び後程説明する秘密証書遺言は、原則遺言者の自宅等で保管をする必要があります。推定相続人に対し作成した旨を知らせる場合もあるかもしれませんが、一般的には、相続人は遺言があるかどうかがよく分からない状態で、遺言があるかどうか、被相続人の住居などをくまなく探すこととなります。また、運悪く他の相続人が遺言を発見し、開封し、中身を確認し、最悪のケースとして破棄してしまった場合には、遺言の存在はなかったものとなってしまいます。遺言の開封は過料の対象ですし、遺言の破棄は相続欠格行為にもなりますが、「バレなければ問題はない」に尽き、自筆証書遺言の地位は非常に不安定です。
なお、これらのデメリットを克服するための制度として、2020年7月10日より法務局で運用されている、「自筆証書遺言保管制度」というものがあります。
自筆証書遺言保管制度については、別ページをご覧ください。
2-1-3.記載方法及びその他の注意点
①曖昧な表現を避ける
遺言内において、相続財産の記載方法や相続分の指定は非常に重要です。それ故、文言によるその特定の方法には十分気を使わないといけません。
例えば、不動産の特定は、不動産登記事項証明書の「表題部」に書かれている地番や家屋番号により行いましょう。住所のみの記載や、「自宅」や「別荘」などの主観的な名称を用いるだけでは、充分な特定がなされない場合があり、争いの火種になりかねません。預金財産については、金融機関・本支店名・種別・口座番号・名義などを間違いの無いように記載しましょう。
また、相続分については、具体的な額や、1/2等により、誰が具体的にどれだけの遺産を取得させるようにしたいのかということを明記しましょう。「誰が」の記載はあっても、「仲良く分けなさい」など、具体的な配分の記載が無ければ同じく争いの原因となってしまいます。
②発見しても、勝手に開封してはいけない
自筆証書遺言を発見した場合、相続人らは家庭裁判所で「検認」を受けなければなりません。検認とは、裁判所において、遺言書の内容や状態などを確認してもらう手続です。封筒などに入っている遺言を検認手続前に開封をしてしまった場合には、過料が課されてしまいますので、検認前の開封は厳禁です。なお、先に述べた自筆証書遺言保管制度を利用し、法務局で自筆証書遺言が保管されている場合には、検認は不要です。
検認手続とは、単に「このような遺言がありました」という存在を証明するだけの手続きであり、遺言の有効性などを担保する手続きではありません。そのため、遺言の有効性や無効性について争いがある場合は、検認後に別に裁判所に調停や訴訟を申立てることとなります。
2-2.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言の内容を秘密にしつつ、遺言の存在を公に証明してもらいたいときに利用すべき遺言です。自筆証書遺言のもつデメリットである、「遺言が存在するか不明確」という部分を克服しつつ、その手続き上、死亡前に誰にも内容を見られることなく作成できるという部分が特徴ですが、近年の法改正や、秘密証書遺言の法制度と他の制度との比較により、利用するメリットがあまり無いというのが正直なところです。
2-2-1.秘密証書遺言作成の流れ
おおまかに説明すると、秘密証書遺言作成の流れは以下の通りとなります。
①遺言書の作成
おおまかな要件は、自筆証書遺言を参考にしていただきたいと思いますが、大きな違いは、遺言者の自筆の署名と押印がなされていれば、他の内容は手書き、パソコン、代筆で記載しても構わないという点です。
②遺言書の封印
作成した遺言を封筒に入れ、遺言書で用いた印で封印をします。
③公証役場で手続
→遺言者が、公証人と証人2人以上の前に封筒を提出し、自己の遺言であること、氏名住所を申述します。証人は、遺言者側で用意する必要がありますが、以下に該当する人は証人にはなれないので注意しましょう。
・推定相続人
・未婚の未成年者
・受遺者及びその配偶者と直系家族
・秘密証書遺言の作成を担当する公証人の配偶者と4親等以内の親族
・公証役場の関係者
④秘密証書遺言の完成
公証人が、その遺言に提出した日付・③によって申述した内容を封筒に記載し、公証人・証人・遺言作成者本人が封筒に署名押印をします。
⑤秘密証書遺言の保管
完成した遺言を持ち帰り、自分で保管をします。
2-2-2.秘密証書遺言による作成のメリット
①内容を秘密にすることができる
秘密証書遺言は、その手続きの流れ上、何人も遺言の内容を確認することはありません(ただし、代筆により作成する場合は別です)。
②偽造や変造を避けられる
遺言の変造や偽造は相続欠格事由となりますが、自筆証書遺言の場合にそれを見破ることは容易ではありません。また、家庭裁判所の検認前に遺言書を開封してしまった場合、過料こそ課されるものの、遺言が無効になることはありません。しかし、秘密証書遺言の場合には公証人が封紙に署名し、封が破られていたり、開かれた跡が残っていたりした場合には、秘密証書遺言は無効となります。そのため、実質的に偽造や変造を避けることが可能となります。
③パソコンや代筆でも作成が可能
これが最大の特徴と言えるかもしれませんが、パソコンや代筆での作成が可能です。ただし、遺言者の自署と押印が必要である点に注意しましょう。
2-2-3.秘密証書遺言による作成のデメリット
①遺言書に不備が残る可能性がある
秘密証書遺言を作成する際、公証人が遺言内容を確認することはありません。そのため、遺言書の要件に沿わない内容であると無効となってしまう場合があります。
ただし、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効となります。この点については、秘密証書遺言による作成を前提として、パソコンもしくは代筆によって作成をしていた場合、自筆証書遺言としても無効となってしまいますので、秘密証書遺言による作成であるとしても、自筆により作成するとよいでしょう。
②手続きの手間や、費用がかかる
後述の公正証書遺言よりは安いものの、手数料として11,000円(税込)がかかります。
また、公証役場に依頼したり、2人の証人を選任したりするというところは公正証書遺言による作成とほとんど変わりがないため、一定の手間と時間がかかります。
なお、証人については、公証役場に相談すれば手配をしてくれます。
③紛失の可能性がある
秘密証書遺言は、公証役場にて作成したという記録は残りますが、遺言書そのものは自分で管理をする必要があります。そのため、万が一紛失した場合には、遺言の内容を確認することはできなくなってしまいます。
④家庭裁判所の検認が必要
秘密証書遺言であっても、自筆証書遺言と同様家庭裁判所での検認が必要となります。
2-2-4.まとめ
以上のことからすると、一定のメリットが存在するのは事実ですが、自筆証書遺言と比べて遺言の有効性が担保されるかというとそうではなく、かといって公正証書遺言と比べて手間がかからないかと言われるとそういう訳でもないため、悪い言い方をすれば中途半端な制度ではないかと思います。ただし、パソコンや代筆による作成が可能という部分は、遺言者自らが作成する遺言としては唯一のメリットであると言えます。
2-3.公正証書遺言
公正証書遺言は、原則的には公証役場において、公証人により作成される遺言です。自筆証書遺言の作成に比べ、公証人関与のもとで作成しますので、有効性のある遺言書を最も確実に作成できる方法と言えます。作成するにあたっては、原則遺言者と証人2名が直接公証役場に出向くということになりますが、もし遺言者が病気や身体上の不自由により出向くことが難しい場合には、公証人が直接遺言者のもとに出張するということも可能となっています。
2-3-1.公正証書遺言作成の大まかな流れ
①公証人との事前打ち合わせ
まずは、公証役場に問合せ、公正証書遺言を作成したい旨を伝えましょう。そうすると、今後の流れや、必要になる書類を教えてくれますので、それらを踏まえ、必要なものを準備していく必要があります。必要になるものは、
・遺言書の案(どのような財産を、誰に、どのように分けたいのか等)
・(受遺者が相続人の場合は)遺言者と相続人の続柄が分かる戸籍謄本
・(受遺者が相続人外の場合は)受遺者の住民票
・財産を証明するもの(預金通帳・不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書)
・遺言者の印鑑登録証明書
・(証人を遺言者側で用意する場合は)証人の基本情報が分かるもの
・(遺言執行者を指定する場合は)遺言執行者の住民票
などです。これらをもとにしつつ、公証人と事前の打ち合わせを行い、遺言書の内容について方向性を決めていくこととなります。全ては、遺言者の遺志を反映させることが大切ですので、遺言書の作成にあたっての細かな点への意向を、説明を受けながら決めていくこととなります。
なお、実務上は、恐らく事前に遺言書の内容となる文面を確認する流れになると思われます。そこで内々の承諾を得た上で、ようやく、本番の作成日を迎えることとなります。
なお、証人の指定については、「2-2-1.秘密証書遺言作成の流れ」③にて記載している方法と同様になりますので、ご参照ください。
②公正証書遺言の作成当日において、遺言書を作成する
①の流れを経て、作成当日を迎えます。当日は原則として、遺言者本人と証人2名が公証役場に出向いた上で、公証人の手で遺言を作成しますが、すでに説明している通り、公証人が出張して、自宅・病院の病室・入所している施設などで作成することも可能です。
当日の大まかな流れとしては、
・公証人挨拶
・遺言者と証人2名に対しての本人確認、質疑
・公証人が筆記した遺言内容を遺言者及び証人に対し読み聞かせる
・遺言者及び証人による署名押印
・公証人による署名押印
となります。
すでに冒頭説明していますが、遺言は、必ず遺言者本人が自らの意思に基づいて作成する必要があります。そのため、遺言者本人への質疑によって、遺言者本人の意思で遺言書の作成が行われることが確認できなければいけません。
③原本は公証役場で保管され、遺言者には正本と謄本が渡される
作成された公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。これにより、遺言書の紛失や隠ぺいはまず間違いなく起きません。その代わりに、遺言者には正本と謄本が渡されます。正本とは、「原本と同じ効力を持つが、関係者の署名押印が省略されたもの」、謄本とは「原本のコピー」です。なお、これらは公証役場にて再発行が可能ですが、遺言者本人が存命中の場合は、遺言者しか再発行の請求ができません。遺言者が亡くなった後は、利害関係人(相続人や受遺者など)が再発行を請求することが可能となります。
2-3-2.その他注意事項
①遺言書作成当日には親族の立ち会いはできない
遺言作成当日は、公証人が遺言内容を遺言者及び証人に対し口述をしますが、これには、遺言者本人と証人2人以外の方が立ち会うことはできません。なぜならば、遺言者本人の真意をきちんと確かめる必要があるからです。逆に、遺言者が1人で公証人からの質疑に応答しないといけませんので、遺言者にとっては非常に緊張するかもしれません。
②作成当日の状況によってキャンセルとなってしまう場合がある
作成当日は、公証人から遺言者及び証人に対して本人確認の他、いくつかの質疑が行われます。既述していますが、遺言者本人の意思による作成であることをきちんと確認する必要があるからです。また、それに加え、遺言者本人が認知症等により意思能力が欠如している等の可能性がないことを確認する必要もあります。ただし、公証人と証人2人しかいない空間で質疑を受けるというのはどうしても緊張してしまうものです。そのような状況下で、ほとんど意思表示ができないという状況に陥ってしまうこともあるようです。とにかく、作成当日に、改めて本人の意思が確認できない場合には、そのままキャンセルという流れになってしまいます。
なお、キャンセルになった場合には、公証役場に対しキャンセル料を支払わなければなりません。
③遺言書の存在の確認は相続人自ら行う必要がある
被相続人が生前公正証書遺言を作成していた場合、被相続人の死亡後、公証役場から遺言の存在について相続人に通知が行くということはありません。なぜなら、公証役場も遺言者の死亡を知ることがないからです。ですから、被相続人が生前公正証書遺言を作成していたかどうかは、相続人が自分で調べる必要があります。
まずは、最寄りの公証役場に訪ねてみるとよいでしょう。公証役場には、遺言書の有無を検索するシステムがあり、全国の公証役場宛てに検索が可能です。ただし、ほとんどの公証役場では、平成以降に作成された遺言書しか保管されていませんので注意が必要です。その際、公正証書遺言の正本または謄本が被相続人の自宅から見つかれば、公正証書遺言があるということが確実に分かるでしょう。
④相続手続は正本または謄本で可能
先ほど説明した通り、作成した公正証書遺言の原本は公証役場で作成され、本人や相続人には正本または謄本が渡されますが、遺言者の死後の相続手続きは、正本又は謄本で十分に手続きが可能です。正本には押印がされておらず、謄本はコピーとなっているため、金融機関の担当者が「原本がなければ手続きができない」と言うことがありますが、原本が持ち出されることはありませんので、その旨をきちんと伝えましょう。
2-3-3.公正証書遺言による作成のメリット
①遺言の有効性が担保される
準国家公務員たる公証人が遺言の作成をしてくれますので、遺言書が無効となる可能性が限りなく低くなります。遺言書には形式上の厳しい要件が求められ、その要件を備えていない限り遺言書は無効となってしまいますし、また、遺言書作成時点の本人の意思能力や認知能力なども問題となりがちです。自筆証書遺言の場合には、本人に相当程度の知識がなければ要件に則った遺言を作成することはできませんし、内容に不満をもった相続人が、本人の意思能力の有無を争って訴訟提起するということもあります。しかし、公正証書遺言の作成においては、公証人が本人確認と本人の意思の確認を厳格に行いますので、公正証書遺言によって作成されているというだけで、これらの点の有効性が担保されているのです。
②公証人が作成手続きを代行してくれる
公証人が遺言者と密に打ち合わせを行いながら代わりに書面を作成してくれますので、例え遺言者の手が不自由で、字が書けないとしても遺言を作成することが可能です。なお、遺言者の手で署名押印することが必要となりますが、この点も事前に公証人に伝えておけば、代わりに署名押印することも可能です。
③家庭裁判所の検認が不要となる
自筆証書遺言のところですでに述べていますが、本来遺言を発見した場合、即座に遺言に基づく相続手続はできないどころか開封すら許されていません。家庭裁判所にて、遺言の存在について「検認」手続きを踏まなければなりませんが、検認が済むまでに多少の期間がかかります。しかし、公正証書遺言については、家庭裁判所の検認が不要となるため即座に相続手続きに移行することが可能です。
2-3-4.公正証書遺言による作成のデメリット
①時間と費用等の手間がかかる
公的機関に作成を依頼しますので、幾何かの費用がかかります。かかる費用としては、
・作成手数料(遺言の目的とする財産の価格によって変動します)
・証人への謝礼(公証役場に選任を依頼した場合に、6,000円~10,000円がかかります)
・弁護士や司法書士等専門家への報酬(作成の手続きを専門家に依頼した場合)
が主となります。また、公証人との打ち合わせを経て作成当日を迎えますので、作成にはどうしても一定期間を要したり、場合によっては複数回公証役場に足を運ぶ必要があったりと手間がかかります。
2-3-5.まとめ
公的機関が遺言書作成の主体となってくれますので、正確で有効性の高い遺言書を作成することが可能です。しかし、その代償といっては何ですが、一定の費用と手間がかかるという点がデメリットとなります。自分の死後に備えて、有効な遺言をきちんと残したいという方にとっては、これ以上ない手段となるでしょう。なお、公証役場との打ち合わせを弁護士等の専門家に任せることも可能ですので、ぜひご検討ください。
3.特別方式による遺言の種類と注意点等
上記で説明した、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言が一般的な形式であるのに対し、緊急時または非常時等において利用が可能な特別方式が存在します。大きく分けて、危急時遺言・隔絶地遺言の2種類、そして危急時遺言として更に一般危急時遺言・遭難船舶危急時遺言が、隔絶地遺言として更に伝染病隔離者遺言・在船者遺言があります。いずれの遺言も、緊急時または非常時に利用するものであることから、一般の形式に比べいくらか要件が緩和されているのが特徴です。ただし、そもそもの利用件数が極めて少数のため、作成においてはより一層の注意を払う必要があります。
3-1.危急時遺言
危急時遺言とは、遺言者に死亡の危急が迫った場合に利用する方式であり、いずれも、遺言者が自筆はもちろん署名押印なども不可能な状況であるため、いくらかの要件が緩和されることになります。なお、遺言の完成後は、作成時の証人1人または利害関係人から、家庭裁判所に申述をし、その確認を得なければ効力を発揮しないこととなっています。危急時遺言には、状況に応じ、「一般危急時遺言」と「遭難船舶危急時遺言」の2種類があります。
3-1-1.一般危急時遺言
「疾病その他の自由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするとき」(民法第976条第1項条文より)に利用する遺言の形式となります。作成の流れとしては、
①証人3人以上が立ち会い、
②そのうちの1人に遺言の趣旨を口授し、口授を受けた者がそれを筆記し、
③筆記した内容を遺言者及びその他の証人に読み聞かせ、内容の正確性を承認し、
④各証人が署名押印をし、
⑤完成した遺言を、遺言の日から20日以内に証人のうちの1人もしくは利害関係人が家庭裁判所に申述する。
となります。
要件が緩和されている部分については、
・本人の自筆である必要がないこと
・本人の署名押印が不要であること
が挙げられます。なお、証人については、秘密証書遺言や公正証書遺言と同様不適格者が存在します。
3-1-2.遭難船舶危急時遺言
遭難船舶危急時遺言とは、「船舶遭難の場合において、船舶中に在って死亡の危急が迫った者」(民法第979条第1項条文より)が遺言を作成する際に利用する遺言の形式となります。船に乗った状態で遭難してしまった状況において、死亡の危急が迫った方が利用する、非常に限定的な方式です。作成の流れは、基本的に一般危急時遺言と同様ですが、さらに要件が緩和され、
・「証人は2人以上でよい」という点
・家庭裁判所への申述が「20日以内」ではなく「遅滞なく」となっている点
が主な緩和事項となります。
3-2.隔絶地遺言
隔絶地遺言とは、遺言者が一般の交通から隔絶した地に在るために、一般の方式による遺言ができない場合に許される特別方式です。これは、遺言者が隔絶した地に在るために、公証人等が関与できず、秘密証書遺言や公正証書遺言の方式による作成が不可能であるという点にあります。危急時遺言との大きな違いは、遺言者に死亡の危急が迫っているか否かという点にあります。ですので、危急時遺言ほど要件が緩和される訳ではない点に注意が必要です。
隔絶地遺言については、「伝染病隔離者遺言」と「在船者遺言」の2種類があります。なお、どちらも作成の要式上、家庭裁判所への申述は不要となっています。
3-2-1.伝染病隔離者遺言
伝染病隔離者遺言とは、「伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者」(民法第977条条文より)が利用する方式です。条文では伝染病と言っていますが、暴動や洪水などにより事実上交通を断たれた場合も含まれるとされています。作成時の注意点としては、
・警察官1人及び証人1人以上の立会いが必要
・遺言者自身が遺言を作成しなければならず、口頭遺言は許されない
・ただし、自筆の必要はなく代筆でもよい
・遺言者、代筆者、立会人及び証人の署名・押印が必要
といったところになります。
3-2-2.在船者遺言
在船者遺言とは、「船舶中に在る者」(民法第978条)が遺言書を作成する際に利用可能な方式となります。作成の流れとしては、伝染病隔離者遺言とほぼ変わらないというところになりますが、船長または事務員1人及び証人2人以上の立会いが必要となります。
3-3.特別方式の遺言における注意点
①署名又は押印ができない者がいる場合の取り扱い
民法第981条では、遺言関係者の署名及び押印について、以下の通り規定されています。
民法第981条
第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。
(民法第981条条文より)
原則として、遺言者・代筆者・立会人・証人などの遺言関係者は、特別方式による遺言の場合でも、遺言への署名押印が求められますが、上記の通り、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人が、遺言書にその事由を付記することで署名又は押印を省略することができます。
ただし、条文をよく見ると分かりますが、第976条(一般危急時遺言)については対象外となっているので注意が必要です。
②家庭裁判所への申述について
既に説明している通り、一般危急時遺言及び遭難船舶危急時遺言については、完成した遺言書について一定期間内に家庭裁判所へ申述をする必要があります。
なお、この際、家庭裁判所においては、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ確認を得ることはできない点に注意が必要です。
さらには、家庭裁判所が心証を得るのは遺言者の真意のみです。遺言の要件については確認の対象とならないため、作成された遺言書について要件の不備などがある場合には、遺言は無効となってしまいます。
4.文言がもたらす効果による遺言の分類
ここまでは、遺言の方式ごとに、どのような要件があり、どのような流れで作成をするのかというところを説明しましたが、実は、遺言の書きぶりによってどのような効果をもたらすかが変わる場合があります。中には、複数の解釈が生まれ、その解釈によって争いが生じるということも珍しくありません。ですから、遺言者は、自分の遺産の分配について具体的にどのような希望を持っているのか、その希望が文面から正確に読み取れるように配慮をしなくてはなりません。
4-1.「遺贈する」と「相続させる」の違い
相手に財産を渡すのだから、上記の2つの違いはないのでは?と思われる方が多いかもしれません。ただし、この2つの文言には大きな違いがあります。
4-1-1.「遺贈する」旨の遺言
そもそも遺贈とは、遺言により特定の人(法人でも可)に無償で財産を譲渡することをいいます。本来、被相続人の財産を相続できるのは法定相続人のみですが、遺贈によって法定相続人外の人や法人に財産を渡すことが可能となります。ですから、「遺贈する」旨の遺言とは、遺贈の効果を発生させる遺言ということになります。
①特定遺贈
特定遺贈とは、遺言の中で「この不動産を遺贈する」とか、「この預金の半分を遺贈する」などのように、遺言者の財産のうち特定の財産のみを遺贈するものを指します。この場合、受遺者(遺贈を受けた者)は、遺贈された財産のみを取得することとなり、例えば、被相続人が多額の負債を抱えているような場合でも、それを負担する義務はありません。
②包括遺贈
包括遺贈とは、遺言の中で「財産を全て遺贈する」とか、「財産の3分の1を遺贈する」などのように、財産を特定せず包括的に割合等を定めて遺贈するものを指します。この場合、受遺者は、遺言者のプラス財産とマイナス財産を全て含めた全ての財産に対し、指定の包括割合で遺贈を受けることとなるため、負債がある場合には、負債も承継することになります。なお、包括遺贈において例えば「財産の3分の1を遺贈する」という内容であった場合、受遺者は遺言者の財産の内どのように3分の1の遺贈を受けるかというところまでは定まっていません。そのため、包括遺贈の受遺者は、相続人と同等の地位に扱われ、遺産分割協議にも参加することとなります。
4-1-2.特定遺贈及び包括遺贈の放棄の仕方
相続人に相続放棄という選択肢が与えられているように、受遺者に対しても遺贈の放棄という選択肢が与えられます。
①特定遺贈の放棄
特定遺贈の放棄は、相続人や遺言執行者に対して遺贈を放棄する旨を通知すれば問題ありません。その方法についても特に指定はありませんが、記録にきちんと残る書面で行う方がよいでしょう。
②包括遺贈の放棄
包括遺贈の放棄の場合、包括受遺者は相続人と同じ立場になります。それ故マイナス財産も承継しなければならない訳ですが、放棄をする場合には、家庭裁判所に遺贈の放棄を申述しなければなりません。なお、相続人と同様、限定承認の申述も可能です。ただし、これまた相続人と同様、包括遺贈があった時から3ヶ月経ってしまうと、自動的に包括遺贈を承継すると承認した(単純承認)ことになりますので注意しましょう。
4-1-3.「相続させる」旨の遺言
対して、「相続させる」旨の遺言とは、遺贈の効果を発生させる遺言ではありません。「相続させる」という文言を考えてみると、相続権は本来法定相続人にしか与えられていません(ただし、相続分の譲渡があった場合を除きます)。ですから、財産を「相続させる」ことができるのは遺言者の推定相続人のみとなります。ここがまず遺贈と異なる点です。また、「相続させる」という文言は、「後の遺産分割方法の一部または全部を指定する」という効果を発生させます。遺贈という行為は相続人に対しても可能ですが、文言ひとつで、もたらす効果が変わることになります。
なお、このような遺言は、「相続させる旨の遺言」と呼ばれていましたが、2019年7月に改正民法が施行され、「特定財産承継遺言」と呼び名が規定されました。条文では、民法第1014条第2項に記載があります。なお、以下の説明では、「相続させる」旨の遺言のことを「特定財産承継遺言」と記載します。
4-1-4.「遺贈させる」旨の遺言と特定財産承継遺言の違い
上記の点も踏まえた上で、特定遺贈・包括遺贈・特定財産承継遺言の違いについては下記の表の通りとなります。
| 種類 | 遺贈 | 特定財産承継遺言 | |
|---|---|---|---|
| 特定遺贈 | 包括遺贈 | ||
| 内容 | 特定の財産を指定して、受遺者に遺贈する | 財産を特定せず、包括的割合によって遺贈する | 「…を相続させる」という文言で、遺産分割方法を指定させる |
| 根拠条文 | 民法第964条 | 民法第964条 | 民法第1014条第2項 |
| 承継者の権利義務 |
・債務は承継しない |
・包括的割合に応じ債務も承継する ・遺産分割協議に参加する |
・遺言の内容によるが、相続人であるため、相続人としての権利義務が発生する |
| 放棄 | 相続人や遺言執行者に対しいつでも放棄の意思表示が可能 ※書面が望ましい |
自分に遺贈があったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し遺贈の放棄または限定承認の申述を行う | 相続があったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に対し相続放棄の申述を行う |
| 承継先の対象 | 相続人、もしくは相続人外の人間や法人に対して可能 | 相続人のみ | |
| 不動産の登記 | ・遺言執行者が指定されている場合、受遺者と遺言執行者が共同で手続きする(実質、受遺者が単独で可能) ・遺言執行者が指定されていない場合、受遺者と相続人全員で手続きする |
遺言執行者もしくは承継者(相続人)が単独で手続きできる | |
| 課税 | ・不動産を承継された場合、不動産取得税がかかる ・登録免許税が相続に比べ高くなる (固定資産評価額×2%) ・受遺者が遺言者の配偶者、子ども、両親以外の場合、相続税が2割加算される |
・不動産取得税はかからない ・登録免許税が相続に比べ高くなる (固定資産評価額×2%) ・受遺者が遺言者の配偶者、子ども、両親以外の場合、相続税が2割加算される |
・不動産取得税はかからない ・登録免許税がかかる (固定資産評価額×0.4%) |
| 相続税の計算方法 | ①相続人以外の人が遺贈を受ける場合、基礎控除額の計算人数には含めずに基礎控除額を算出する ②相続財産の取得割合に応じて相続税を振り分ける際には、相続人以外の人(受遺者)も含めて税額を決める |
||
相続人に対し財産を承継させる場合には、遺贈と特定財産承継遺言の両方を選択することが可能ですが、上記のような違いがありますので、状況に応じて判断をする必要があります。なお、遺贈にかかる税は、贈与税ではなく相続税です。贈与税とは、生前の贈与にのみかかる税となります。よって、死因贈与の場合にも相続税が課されます。
5.まとめ
遺言を作成する大きな目的は、やはり特定の人間に財産を遺すことにあると考えられます。相続人や受遺者のことを思い、あれこれ方法を考えながら遺言を作成することと思いますが、どの方式で遺言を作成するにしても、その要件を厳格に守り、文言ひとつひとつに配慮しながら作成することが求められます。ここで説明した事項以外にも、細かい規定が絡み合うため、一般の方が自分の力のみで遺言を作成するというのは大変難しいのではないでしょうか。
せっかく相続人のためを思い作成した遺言が、かえって相続問題を招く種となりかねません。遺言の作成をお考えの方は、ぜひ、弁護士への相談をご検討ください。